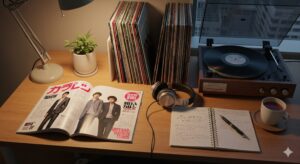大切なレコードを最高の音質で楽しむためには、盤面のコンディションを良好に保つことが欠かせません。そのためには、レコードクリーナー選びで失敗しないための知識は不可欠です。この記事では、まず乾式クリーニングの正しい使い方やコツ、そしてブラシやクロスといったおすすめのキットや液の選び方について解説します。また、悩みの種である針の音飛びやカビは、体の静電気や適切な乾燥で対策できることもご存知でしょうか。100均製品での代用や自作、ウタマロの使用がなぜ危険なのか、そしてアルコールやアルカリ電解水の使用に関する注意点も詳しく掘り下げます。さらに記事の後半では、具体的なおすすめレコードクリーナーと購入ガイドとして、定番のオーディオテクニカ製品であるat6012aとat6018aの違いから、ナガオカのアルジャント120やドライウェルの特徴、boundless audio、オルトフォン、oyag、ka rc 1といった人気ブランドまで網羅します。本格的なエストニア製の機械やキースモンクスのアーム型クリーナーにも触れていきますので、ご自身のスタイルに合った製品が見つかるはずです。購入先として便利なamazonやヨドバシ、専門店ならではの品揃えが魅力のdisk unionやタワレコでの探し方も紹介。この記事を読めば、大切な浦沢直樹の盤も守れるような、あなたに最適なレコードクリーナーがきっと見つかります。
-
- レコードクリーナーの基本的な種類と選び方がわかる
- 乾式・湿式クリーニングの正しい手順と注意点が身につく
- オーディオテクニカやナガオカなど人気ブランドの製品特徴を比較できる
- 目的や予算に合わせた最適なクリーナーの購入場所が見つかる
レコードクリーナー選びで失敗しない知識
- 乾式クリーニングの正しい使い方とコツ
- ブラシやクロスなどおすすめキットと液
- 針の音飛びやカビは体の静電気と乾燥で防ぐ
- 100均での代用や自作、ウタマロは危険
- アルコールやアルカリ電解水の使用注意点
乾式クリーニングの正しい使い方とコツ

レコードの世界:イメージ
レコードクリーニングの第一歩であり、最も基本的なメンテナンスが「乾式クリーニング」です。これは、レコードをプレーヤーで再生する直前に、盤面に付着した表面的なホコリやチリを手軽に取り除く作業を指します。いわば、レコード鑑賞前の「儀式」とも言えるでしょう。
この工程の主な目的は、再生中にスタイラス(レコード針)がホコリを拾うことで生じる耳障りな「パチパチ」というスクラッチノイズを最小限に抑えることにあります。また、針先にホコリが雪だるま式に固着し、音溝の正確なトレースを妨げるのを防ぐという重要な役割も担っています。高価な専用機材を必要とせず、レコードブラシ一本で始められる手軽さが、乾式クリーニング最大のメリットです。
乾式クリーニングの基本的な手順(ターンテーブル使用時)
- まず、レコードをターンテーブルのプラッターに静かに乗せ、回転させます。
- カーボンブラシなどの乾式クリーナーを、レコード盤の半径に対して垂直になるように持ち、ごく軽い力で盤面に当てます。ブラシの自重だけで十分です。
- レコードを数周回転させ、ブラシの繊維が盤面のホコリを確実に捉えているのを確認します。ホコリが一筋の線となって集まってくるのが見えるはずです。
- ブラシを傾けたりせず、垂直に保ったまま、ゆっくりとレコードの外側(または内側)へスライドさせます。これにより、集めたホコリを盤の外へと効果的に掃き出すことができます。
絶対に避けるべきNG行為
クリーナーを強く盤面に押し付けるのは逆効果です。表面のホコリを音溝のさらに奥深くへと押し込んでしまい、かえってノイズの原因を深刻化させる恐れがあります。また、CDをクリーニングする時のように、盤の中心から外側へ向かって直線的に拭く動作は絶対に避けてください。レコードの音溝は渦巻状に刻まれており、この流れに逆らう動きは、盤面に微細な傷(スレ)を付ける原因となり得ます。クリーニングは、必ず音溝に沿って円を描くように行うのが鉄則です。
ブラシやクロスなどおすすめキットと液

レコードの世界:イメージ
効果的なレコードクリーニングを行うためには、用途に応じた適切な道具を揃えることが不可欠です。ここでは、クリーニングの基本となる道具の種類と、それぞれの役割について詳しく解説します。
クリーニングブラシ:用途で使い分ける2大タイプ
乾式クリーニングの主役となるブラシには、主に2つのタイプが存在します。
- カーボンファイバーブラシ: 数ミクロン単位の非常に細いカーボン繊維が、肉眼では見えない音溝の奥深くまで入り込み、微細なホコリを効果的にかき出す能力に長けています。同時に、導電性を持つカーボン繊維がレコード盤の表面に帯電した静電気を効率的に除去する効果があり、ホコリが再び吸い寄せられるのを防ぎます。日常的な再生前のクリーニングには、最も適したブラシと言えるでしょう。
- ベルベットブラシ: ベルベット状の柔らかく高密度な生地で、盤面の汚れを優しく拭うタイプのブラシです。広い接触面で、比較的大きなホコリや指紋などを捉えるのに適しています。多くの製品は、後述する湿式クリーニング用のクリーニング液と併用することを想定して設計されています。
クリーニングクロス:繊細な仕上げの必需品
クリーニングクロスは、主に湿式クリーニングの際にクリーニング液を拭き取ったり、最終的な仕上げ磨きに使用したりします。素材としては、極細の繊維で織られたマイクロファイバー製のものが主流です。重要なのは、ケバ立ちが少なく、繊維が抜け落ちにくい高品質な専用品を選ぶことです。安価なメガネ拭きや家庭用クロスで代用すると、拭き取り時に繊維が抜け落ち、それが新たなゴミとして音溝に残ってしまう本末転倒な事態になりかねません。
クリーニング液(クリーナー液):汚れの種類に応じて
乾拭きだけでは除去が難しい、指紋などの皮脂汚れ、油性の汚れ、あるいは不幸にも発生してしまった軽いカビなどを化学的に浮かせて除去するために使用します。主成分によって、アルコールを含むタイプ、含まないアルコールフリータイプ、電解水をベースにしたタイプなど、多種多様な製品が存在します。これら液剤の特性と注意点については、後の見出しでさらに詳しく解説していきます。
入門者にはまず「クリーニングキット」が最適解
「何から揃えれば良いのか全く分からない」という方には、ブラシ、クリーニング液、クロス、時にはスタイラスクリーナーまでが一つになった「クリーニングキット」の購入を強くおすすめします。クリーニングに必要な基本アイテムが一通り揃っているため、迷うことがありません。個別に購入するよりもコストパフォーマンスに優れている場合が多く、レコード入門者へのプレゼントとしても喜ばれるでしょう。
針の音飛びやカビは体の静電気と乾燥で防ぐ
アナログレコードの再生において、リスニング体験を著しく損なう二大トラブルが「針の音飛び」と「カビの発生」です。これらは一度発生すると対処が厄介ですが、原因を理解し、日頃から適切な対策を講じることで、その発生リスクを大幅に低減させることができます。
針の音飛びの隠れた原因「静電気」とその対策
針の音飛びの直接的な原因は、音溝に詰まったホコリやゴミがスタイラスの正常なトレースを物理的に妨げることです。しかし、その根本的な原因、つまり「なぜホコリが付着するのか」という点に目を向けると、「静電気」の存在が大きくクローズアップされます。
レコードの主原料である塩化ビニルは、摩擦によって非常に静電気を帯びやすい性質を持っています。特に、気象庁が注意を促すような空気が乾燥した冬場には、レコード盤は数千ボルトもの静電気を帯電することがあり、これが強力な磁石のように空気中のホコリを盤面へと引き寄せてしまうのです。 対策として最も有効なのは、前述したカーボンファイバーブラシによるこまめな除電です。多くのブラシは持ち手の一部が金属製になっており、その部分に触れながらクリーニングすることで、レコード盤の静電気をブラシ→自分の体→床や大地(アース)へと逃がすことができます。
レコードに触れる前に、部屋のドアノブなど、大きな金属部分に一度触れて自分自身の静電気を放電しておく「セルフアース」も、簡単ながら非常に効果的な対策ですよ。
カビ発生の温床「湿気」とその対策
レコードにとって最大の敵とも言えるカビは、「湿気」、すなわち高い湿度が最大の原因です。日本の気候は高温多湿であり、特に梅雨の時期や夏場は注意が必要です。一度レコードの音溝にカビが根を張ってしまうと、完全な除去はプロのクリーニングサービスでも困難を極めます。カビは再生時に持続的なノイズを発生させるだけでなく、盤面を侵食し、レコードの資産価値を大きく損ないます。
カビ対策の鉄則は「徹底した乾燥」と「適切な保管」
湿式クリーニングを行った後は、何をおいてもレコード盤を完全に乾燥させることが絶対的な鉄則です。専用のレコード乾燥台(ディスク乾燥スタンド)などを活用し、風通しの良い日陰で、盤面がサラサラになるまで時間をかけてしっかりと乾かしましょう。生乾きの状態でジャケットや内袋に戻す行為は、自らカビの培養ケースを作っているようなものです。
また、日常的な保管場所の選定も極めて重要です。直射日光が当たる場所や、押し入れ、地下室などの湿気がこもりやすい場所は避け、風通しが良く、温度・湿度の変化が少ない場所で保管することを強く推奨します。
100均での代用や自作、ウタマロは危険

レコードの世界:イメージ
レコードクリーナーは専用品が多いため、ある程度のコストがかかります。その手軽さから「身近な日用品で代用できないか」という考えが頭をよぎるかもしれませんが、その考えはあなたの貴重なレコードコレクションを深刻な危険に晒す行為であり、絶対に避けるべきです。
安易な代用が引き起こす、取り返しのつかないトラブル
- 100均のブラシやクロス類: 100円ショップで販売されている様々な掃除用ブラシやマイクロファイバークロスは、一見するとレコードにも使えそうに思えるかもしれません。しかし、それらの製品はあくまで一般的な家庭の清掃用途に作られたものです。繊維の硬さ、太さ、密度、耐久性がデリケートなレコードの音溝をクリーニングするには全く適しておらず、音溝の摩耗や微細なスクラッチ(傷)の原因となります。また、繊維が抜け落ちやすく、それ自体が新たなゴミとして音溝に詰まるリスクも非常に高いのです。
- 自作クリーニング液(中性洗剤など): 食器用の中性洗剤や、人気のウタマロクリーナーなどを水で薄めて自作する、という情報をインターネット上で見かけることがありますが、これも非常に危険な行為です。これらの洗剤に含まれる界面活性剤やその他の化学成分が、乾燥後も音溝の底に目に見えない膜となって残留します。この残留物は、再生時のノイズの原因となるだけでなく、湿気を吸着し、カビの絶好の栄養源となってしまう可能性があります。
- ウタマロクリーナーの危険性: 特にウタマロクリーナーは、その高い洗浄力から万能とされがちですが、レコードの主成分である塩化ビニル(PVC)に対してどのような化学的影響を及ぼすか全く保証されていません。レコードの洗浄を目的としていない化学製品の使用は、絶対に避けるべきです。
メーカーが開発・販売する専用のクリーナーやクリーニング液は、デリケートなレコードの音溝を物理的・化学的に傷つけることなく、かつ洗浄成分が盤面に残らないよう、研究を重ねて設計されています。目先のわずかなコストを惜しんだ結果、二度と元には戻らない致命的なダメージを愛聴盤に与えてしまっては、後悔してもしきれません。レコードのメンテナンスには、必ず専用品を使用しましょう。
アルコールやアルカリ電解水の使用注意点
一口に専用クリーニング液と言っても、その主成分によって特性は様々です。ここでは、代表的な成分である「アルコール」や「アルカリ電解水」をベースにした製品について、それぞれのメリットと、使用する上で必ず知っておくべき注意点を詳しく解説します。
アルコール(酒精)を含むクリーニング液
メリット: アルコール類の最大の利点は、その揮発性の高さにあります。速乾性に優れているため、クリーニング後の拭き跡が盤面に残りにくく、作業性に優れています。また、指紋などの皮脂汚れをはじめとする油性の汚れに対して、高い洗浄力を発揮するとされています。
デメリット・注意点: 一方で、使用するアルコールの種類(エタノール、イソプロピルアルコールなど)や濃度によっては、レコード盤の素材である塩化ビニルを僅かに侵食したり、盤の柔軟性を保つために添加されている可塑剤に悪影響を与えたりする可能性がある、という専門家からの指摘もあります。特に、SP盤の主原料であるシェラック樹脂はアルコールに溶解するため、SP盤へのアルコール含有液の使用は絶対に禁忌です。一般的なLP盤に使用する場合であっても、必ず「レコード専用」として成分調整された製品を選び、過度な頻度での使用は避けるのが賢明です。
アルカリ電解水ベースのクリーニング液
メリット: アルカリ電解水は、水を電気分解して作られる洗浄水で、界面活性剤やアルコール、その他の化学物質を一切含まない点が最大のメリットです。そのため、レコード盤や人体、環境への負荷が極めて少ないとされています。洗浄後に盤面に残るのは純粋な水だけなので、成分残留の心配がほとんどありません。
デメリット・注意点: 洗浄力は比較的穏やかで、固着してしまった強力な油汚れなどに対しては、アルコール系のクリーナーに一歩譲る場合があります。また、市場には様々なアルカリ電解水製品が出回っており、その品質や生成方法は一様ではありません。こちらも信頼できるオーディオアクセサリーメーカーから、明確に「レコードクリーニング用」として販売されている製品を選ぶことが、安全と安心に繋がります。
選択に迷ったら、まずは「アルコールフリー」の専用液を
初めてクリーニング液を選ぶ方や、貴重盤・デリケートな盤をクリーニングする際には、リスクを最小限に抑えるためにも、「アルコールフリー」と明記されたレコード専用クリーナーを選ぶのが最も安全で賢明な選択肢と言えるでしょう。
おすすめレコードクリーナーと購入ガイド

レコードの世界:イメージ
- オーディオテクニカat6012aとat6018a
- ナガオカのアルジャント120とドライウェル
- boundless audio、オルトフォン、oyag、ka rc 1
- エストニア製機械やキースモンクスのアーム
- amazon、ヨドバシ、disk union、タワレコ
- 浦沢直樹の盤も守れるレコードクリーナー
オーディオテクニカat6012aとat6018a
マイクロフォンやヘッドホン、そしてカートリッジなど、多岐にわたる音響機器で世界的に高い評価を得ている日本の雄、オーディオテクニカ(audio-technica)。同社はレコードアクセサリーの分野でも長い歴史と実績を誇り、その製品は入門者からオーディオ愛好家まで、世代を超えて幅広く支持されています。中でもレコードクリーナーの定番として特に人気が高いのが、湿式と乾式の両方に対応する2つのロングセラーモデル、AT6012aとAT6018aです。
どちらのモデルも数十年にわたって基本的なデザインを変えずに販売され続けていること自体が、その完成度の高さを物語っています。迷ったらまずこの2つのどちらかを選んでおけば、まず後悔することはないでしょう。
両モデルの基本的な使い方は同じですが、クリーニング性能の要となるベルベット部分の素材と、使い勝手を向上させる付加機能に違いがあります。どちらがご自身の使用スタイルや求めるクリーニングレベルに合っているか、以下の比較表を参考にじっくりとご検討ください。
| 項目 | AT6012a(スタンダードモデル) | AT6018a(上位モデル) |
|---|---|---|
| 特徴 | 基本性能をしっかり押さえた定番 | より高い洗浄力を追求した高性能版 |
| ベルベット素材 | 導電性フェルトを採用した高密度ベルベット | クリーニング性能に特化した「方向性ベルベット」を採用 |
| クリーニング性能 | 日常的なホコリや表面の汚れを確実に除去 | 音溝の奥深くにある微細なチリまで効果的に絡め取る |
| 付加機能 | シンプルで直感的な操作性 | カラーインジケーターにより、液の浸透度合いを視覚的に確認可能 |
| 価格帯 | 比較的安価で入手しやすい | AT6012aに比べて高価 |
| こんな方におすすめ | 初めてレコードクリーナーを購入する方、コストを抑えたい方 | 中古盤を多く扱う方、より完璧なクリーニング効果を求める方 |
上位モデルであるAT6018aに採用されている「方向性ベルベット」とは、繊維の毛の流れが一方向に精密に揃えられた特殊な素材です。指定された方向に沿って拭き上げることで、汚れを一方通行で効率的にかき出すことができ、より高いクリーニング効果を発揮します。また、本体側面に設けられたカラーインジケーターは、内部に注入したクリーニング液がベルベット面に適正量染み込んでいるかを色で知らせてくれる便利な機能です。これにより、液の付けすぎによる盤面への悪影響や、液の無駄遣いを防ぐことができます。
もちろん、スタンダードモデルのAT6012aでも基本的なクリーニング性能は非常に高く、日常的なメンテナンスには十分すぎるほどです。ご自身の予算や、どれくらいのレベルのクリーニングを求めるかに合わせて選ぶのが良いでしょう。(参照:オーディオテクニカ公式サイト アクセサリーページ)
ナガオカのアルジャント120とドライウェル
1940年の創業以来、レコード針(カートリッジ)一筋に開発を続け、その品質で世界中のレコードファンやDJから絶大な信頼を得ている老舗メーカー、ナガオカ(NAGAOKA)。同社が手がけるレコードアクセサリーは、レコード再生のメカニズムを知り尽くした専門メーカーならではの深い知見に基づいて設計されており、多くの愛好家に長く愛用されています。
湿式クリーナーの代名詞「アルジャント CL120」
「アルジャント(ARGENTO) CL120」は、ナガオカを代表するベルベットタイプの湿式クリーナーです。使い方は非常にシンプル。レコード盤面に付属のクリーニング液(クリアトーン558)を2、3滴垂らし、アルジャント本体のベルベット面で音溝に沿って優しく拭き上げるだけ。この簡単な作業で、乾拭きでは取れない指紋などの頑固な汚れや、静電気を手軽かつ効果的に除去することができます。
人間工学に基づいた握りやすいグリップ形状と、デリケートなレコード盤を絶対に傷つけることがないよう緻密に設計されたベルベット面が、長年にわたり支持され続ける理由です。クリーニング液がなくなっても、補充用のスプレーが単体で販売されているため、本体を長く経済的に使い続けることが可能です。
レコード乾燥の決定版「ドライウェル」
前のセクションでも強調した通り、湿式クリーニングにおいて最も重要な工程の一つが、洗浄後の「乾燥」です。この工程を疎かにすると、カビという最悪の事態を招きかねません。そこで絶大な効果を発揮するのが、ナガオカのレコード乾燥専用スタンド「ドライウェル」です。
「ドライウェル」がもたらす3つのメリット
- 究極の安全性: レコード同士が適切な間隔を保って立てかけられるため、盤面が接触して傷が付いたり、大切なレーベル面が汚れたりする心配がありません。
- 圧倒的な作業効率: 一度に最大10枚(モデルによる)のレコードを同時に乾燥させることができます。複数枚のレコードをまとめてクリーニングする際の作業効率が劇的に向上します。
- 優れた収納性: 使用しないときはコンパクトに折りたたむことができ、収納場所に困りません。
湿式クリーニングを定常的に行うのであれば、レコードをカビのリスクから確実に守るためにも、ぜひ導入を検討したい必須アイテムの一つと言えるでしょう。
boundless audio、オルトフォン、oyag、ka rc 1
日本の定番メーカー以外にも、世界には個性豊かで魅力的なレコードクリーナーを開発・販売しているブランドが数多く存在します。ここでは、近年特に注目度が高まっているブランドと、その代表的な製品をいくつかご紹介します。
Boundless Audio(バウンドレス・オーディオ):初心者のための完璧なスタートキット
アメリカを拠点とするBoundless Audioは、洗練されたモダンなデザインと、考え抜かれた実用性を両立させたクリーニングキットで世界的な人気を博しているブランドです。主力製品であるクリーニングキットには、ベルベットブラシ、カーボンファイバーブラシ、スタイラス(針)専用クリーナー、アルコールフリーのクリーニング液、そしてそれら全てをスマートに収納できる専用バッグまでが同梱されており、これからレコードのある生活を始める人が、最初に手に入れるべき完璧なオールインワンパッケージとして非常に高い評価を得ています。
Ortofon(オルトフォン):カートリッジメーカーの哲学が宿る逸品
100年以上の歴史を誇るデンマークの老舗カートリッジメーカーOrtofonもまた、純正のレコードブラシをラインナップしています。一見するとシンプルなカーボンファイバーブラシですが、レコードの音溝とスタイラスの関係性を誰よりも深く理解しているメーカーが作ったという事実こそが、最大の信頼性の証です。ミニマルで美しいスカンジナビアンデザインも魅力で、ただの道具としてだけでなく、プレーヤーの傍らに置いておきたくなる所有欲を満たす逸品です。
OYAG SOUND(オヤッグ・サウンド):ヘビーユーザーの強い味方
OYAG SOUNDは、優れたコストパフォーマンスで日本のレコード愛好家から熱い支持を集めている国内ブランドです。特に大容量で価格も手頃なクリーニング液「OYAG33」は、「盤面の汚れを気にせず、気兼ねなくたっぷりと使える」と、中古盤を大量に購入・洗浄するヘビーユーザーにとって無くてはならない存在となっています。
ka rc 1:新たな選択肢として
ka rc 1は、特定のブランド名というよりは、主に海外のECサイト(電子商取引サイト)を中心に見られる、比較的新しいクリーニング製品群のモデル名や型番の一つです。その多くは、ベルベットブラシやカーボンブラシ、クリーニング液などがセットになったキット形式で販売されています。品質は様々ですが、Boundless Audioと同様に、初心者向けのオールインワンパッケージとして、新たな選択肢に入ってくる存在です。
エストニア製機械やキースモンクスのアーム
日常的な手作業によるクリーニングからさらにステップアップし、より完璧で徹底的な洗浄を求める熱心なオーディオファイルのためには、高度な技術を用いた専用のクリーニングマシンが存在します。これらのマシンは非常に高価ですが、手作業では決して到達できないレベルの、圧倒的な洗浄効果をレコードにもたらします。
超音波式レコードクリーナー:非接触洗浄の極致(エストニア製など)
近年のレコードクリーニング技術において、最も革新的で注目を集めているのが「超音波洗浄機」です。基本的な原理は、メガネや貴金属の洗浄に使われるものと同じ。洗浄槽に満たした精製水や専用の洗浄液にレコードを浸し、高周波の超音波を照射します。すると、液体中にマイクロメートル単位の無数の真空の泡が発生し、これが破裂(キャビテーション)する際の衝撃波を利用して、音溝の奥底に固着した微細なホコリやカビ、油汚れまでを物理的に剥がし取ります。
この分野では、北欧の技術国エストニアのDegritter社などが世界的に有名で、洗浄から乾燥までを全自動で行う、洗練されたデザインの高性能なモデルを開発しています。レコード盤面にブラシなどが一切触れることなく(完全非接触で)洗浄できるため、盤面への物理的ダメージが最も少ない、究極のクリーニング方法の一つとされています。
超音波洗浄機の導入における注意点
導入の最大の障壁は、数十万円からという非常に高価な価格帯です。また、製品によっては動作音が大きいものや、連続使用によって洗浄液の水温が上昇し、熱に弱いレコード盤に影響を与える可能性があるため、冷却機能や水温管理システムといった安全対策がしっかりと施された、信頼できるメーカーの製品を選ぶことが極めて重要です。
キース・モンクス(Keith Monks)のアーム型クリーナー:プロが認める伝統のバキューム式
キース・モンクスは、「バキューム式レコードクリーナー」というジャンルを確立した、草分け的存在として知られる英国の伝統的なブランドです。その最大の特徴は、レコード盤上をあたかもトーンアームのようにゆっくりと動く、ユニークな「クリーニング・アーム」にあります。
このアームの先端から盤面にクリーニング液を精密に塗布し、それと同時に、塗布された液を盤面の汚れごと、アーム内部を通じで強力なポンプで吸引(バキューム)する仕組みです。洗浄液が盤面に残留する時間が極めて短く、汚れの再付着が起こらないため、非常に高いクリーニング効果を発揮します。その信頼性の高さから、世界中の放送局や図書館、アーカイストといったプロフェッショナルの現場で長年にわたり標準機として使用されてきた実績があります。
amazon、ヨドバシ、disk union、タワレコ

レコードの世界:イメージ
自分に合ったレコードクリーナーを見つけたら、次にどこで購入するかを考えましょう。オンラインストアから専門店まで、それぞれにメリットとデメリットがあります。目的や状況に応じて賢く使い分けるのがおすすめです。
| 購入場所 | メリット | デメリット | こんな時におすすめ |
|---|---|---|---|
| Amazon | 国内外のブランドを網羅した圧倒的な品揃え。価格比較が容易で、多数のユーザーレビューを参考にできる。 | 品質が不確かなノーブランド品も多く、玉石混交の状態。製品知識がないと選択が難しい場合がある。 | Boundless Audioのような海外の人気ブランド製品や、定番クリーナーの補充液などを探すのに最も便利。 |
| ヨドバシカメラ | オーディオテクニカやナガオカといった国内主要メーカーの定番品が豊富。在庫があれば即日入手可能。ポイント還元も魅力。 | キース・モンクスのような専門的・マニアックな海外製品の取り扱いは少ない傾向にある。 | 国内メーカーの定番品を、実際に手に取って質感などを確かめてから購入したい場合や、急に必要になった場合に最適。 |
| disk union | レコード専門店の知識豊富なスタッフが厳選した、信頼性の高い製品のみが並ぶ。同社オリジナルのクリーニンググッズも人気が高い。 | 実店舗が都市部に集中しているため、地方在住の場合はオンラインストアの活用が基本となる。 | OYAG SOUNDの製品や、お店独自の視点でセレクトされたこだわりの逸品、プロユースのアクセサリーを探すのに向いている。 |
| タワーレコード | 近年レコードの販売に再び力を入れており、レコードを購入する層に向けた入門者向けのクリーニングキットなどを中心に取り扱っている。 | オーディオ専門店に比べると、アクセサリー全体の品揃えは限定的。 | レコードを買いに行ったその足で、とりあえず基本的なクリーニング用品一式を揃えたい、という場合に便利。 |
まとめ:この記事のポイント
この記事で解説してきた様々な知識とテクニックを実践すれば、あなたの大切なレコードコレクションを、購入した時のような、あるいはそれ以上の輝きを持つ状態で、これから先も長く楽しむことができます。最後に、この記事の重要なポイントをリスト形式で振り返っておきましょう。
- レコードクリーニングは日常的な手入れの「乾式」と徹底洗浄の「湿式」を使い分ける
- 乾式クリーニングは再生直前の表面的なホコリ除去を目的とする
- クリーナーは盤の回転方向に逆らわず必ず音溝に沿って円を描くように動かす
- ブラシは静電気除去効果を併せ持つ高品質なカーボンファイバー製が基本におすすめ
- 湿式クリーニングを行った後はカビ発生を防ぐために完全な乾燥が絶対条件である
- 100均グッズや中性洗剤、ウタマロなどでの安易な代用はレコードを傷つけるため絶対NG
- クリーニング液はリスクの少ない「アルコールフリー」と明記された専用品から試すのが最も安心
- オーディオテクニカのAT6012aは品質と価格のバランスに優れた入門に最適な定番モデル
- より高い洗浄力や利便性を求めるなら上位モデルのAT6018aも有力な選択肢となる
- ナガオカのアルジャントは長年の実績を持つ信頼性の高い湿式クリーナーの定番である
- 初心者は必要な道具が一式揃ったBoundless Audioなどのクリーニングキットから始めるのが手軽
- 究極の洗浄を求めるオーディオファイルには超音波式やバキューム式の専用マシンもある
- 購入はAmazonの圧倒的な品揃え、ヨドバシの即納性、disk unionの専門性を賢く使い分ける
- クリーニングは音質向上だけでなくジャケットを含めた文化財保護という高い意識を持つ
- 自分に合った最適なレコードクリーナーを見つけて豊かで素晴らしいアナログライフを送る